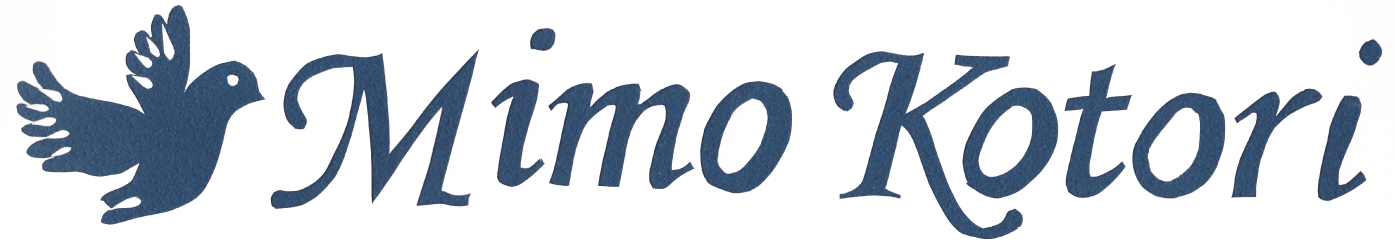年老いてきた母には様々なサポートが必要。必要なとき、必要なこどもが登場して、母をサポートしている。四人兄弟だから手を取り合って、連絡を取り合って。とはいえ、わたし以外の兄弟は皆が東京在住。わたしが一番母のところへ通えておらず、せめてと、行くときは大抵お泊まりをしている。ばあばのことが大好きな娘も必ずついてくるので、三世代で過ごす。これがなかなか愉快なのだ。
母が今住んでいる吉祥寺という街は、デパート、雑貨屋、カフェ、レストラン、公園、なんでもそろう。しかし、娘のリクエストは大抵がサイゼリア。先日も三世代で夕飯を食べに。我々が通された席、その隣のテーブルは白髪で長髪の、おそらくヨーロッパ系の男性が一人、すでに二つ目のデキャンタが空になっていた。男性がわたしの母に話しかけてきたのを、娘が怖がっているのは一目瞭然だった。おじさんと目が合わないようにと、硬直していた10歳を、わたしは見ていた。
運ばれてきた料理を食べていると、フロアを縦横無尽に歩き出す別の男性があらわれた。この連日の酷暑の中、Tシャツの上に汚れきったトレンチコート、チャックが開いたままのズボン、靴は見るまでもなかった。お腹が空いているのか、席に座らずうろうろする男性を、途中何度か若い店員たちがたしなめる。やっと席につくと、我々の席の近くのドリンクバーにやってきた。その途中に、背後から娘にニコニコと近づいてきて、「おかあさんたちに、かわいいまるい目をもらってよかったねえ」と声をかけてきた。娘、硬直。わたしと母は、目でニコッとおじさんに合図しておしまい。おじさんが立ち去るや否や、娘が一言、「こわっ」と言った。そしてもう一言、「きもっ」と言ったときだ。「こわいはいいけど、きもいはだめだよ」、間髪入れず、娘にボールを打ち返した。「ママはあの人、そんなに悪い人に見えなかったよ。ニコニコした目の奥が、きれいだなって。あのトレンチコートも、もともとは悪いものじゃないとおもうよ。うまくいっていた事業が失敗したとかね、人生は色々あるんだよ。みんな色々なんだよ。だから、こわいはいいけれど、きもいはだめだよ。そう言うことを言ってはだめ」とわたし。「ばあばとママは怖くないの?」と娘が言うので、「馬場(わたしが生まれ育った高田馬場)なんて、あんな感じの人普通にいっぱいいたよね?」と言うと、「そうねえ、いろんな人がいたわね」とばあば。
わたしがいちばん怖いな、悲しいなと思うのは、そのようなおじさんたちではない。そうではなくて、きれいなものに囲まれたきれいなお店で働いているのに、目に力のない若者を見るときが、本当にいちばんつらい。美しい製品なのに棚に埃がかぶっていたり、製品がくたびれて並んでいるのに気が付くときも、なんだかとっても悲しい。もっと自由に生きていいし、やりたくないことを嫌々やるほど、人生は長くない。どんな仕事も楽しみを見つけてほしい。探しても見つけられなかったら、飛び立っていいんだよと、くたびれた若者を見るたびに思う。そんなに何度も「申し訳ございません」を連発しなくていい。なにも申し訳なく、ないんだよ。心の中で思うけれど、「ありがとう」以外は何も言わない。誰も助けてくれないから、自分で、自分を最高な場所に運ぶんだよ。若いときは、たくさん挑戦して、同じだけ失敗もできるんだから。それが若者の特権なんだって、若い頃には気付きにくいのだろう。