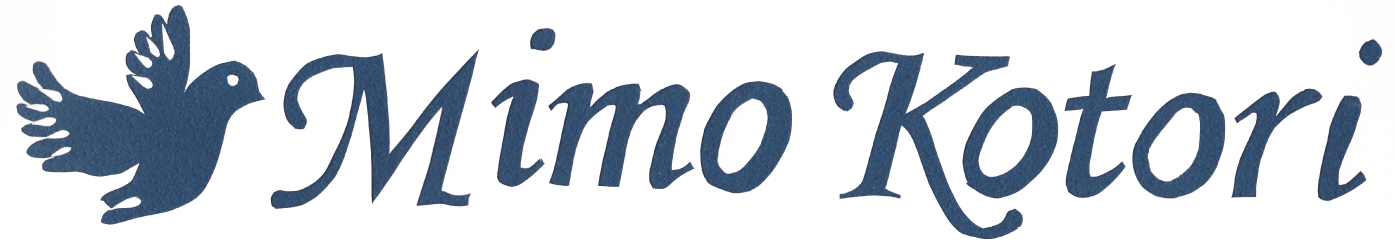営業や販売とはなにか。そのことを教えてくれた人が、ふたりいる。
ひとりは父。家業を継いでいた父は、根っからの営業マンだった。本人のキャラクターのなせる技もおおきいとは思うが、「常に心に営業を」みたいな人で、家でもよく、晩酌をしながら営業先でのはなしなどをしていた。実に楽しそうに。家では仕事の話をしないお父さんだった、みたいなことをときどき聞くが、父は真逆だった。家族で誰もわかる人がいないのに、気にせずにしゃべっていた。
切り絵作家の夫が、東京ではじめての個展をすることになったときのことだ。父にDMを郵送してお知らせをすると、それを見た父からすぐに電話がかかってきた。「あのハガキ、まだあるならパパのところに何枚か余分におくってくれよ」とのことだった。あとでわかったことだが、父は自分の友人などにもお知らせをしてくれていたのだ。たとえばマガジンハウスで働いていた同級生など、どこかのなにかに引っ掛かるかも? と父のセンサーがはたらいた人には、長文の手紙を添えてDMを送ってくれていたそうだ。母がおしえてくれ知った。実家のあった高田馬場には、近所に、週末になると千葉県から軽トラックで野菜を売りにくる農家の老夫婦がいた。父はそのご夫婦をやたらと好いていて、毎週欠かさず足を運んでいた。その日、わたしは夫の展示の手伝いで、実家に連泊していた。久しぶりにそのトラックを見かけたので挨拶をしたら「おとうさんが、娘さんのご主人の切り絵展ですか?ハガキをくれてね」と声をかけられた。「お父さま、『なんだかよくわかんないんだけどさ、よかったらいってやってよ』って」と。笑ってしまった。と同時に、ものを売るってこういうことなのかと、ゆるゆるな頭を殴られたような衝撃を受けた。
ふたりめは展示場所で何度もお世話になった『Zakka』で、公私にわたって面倒をみていただいた写真家の北出博基(きたで・ひろき)さん。展示の前日、切り絵の搬入と設営を終えて一息ついていたら、「みもちゃん、これが全部売れたらいくら?」と聞かれた。すぐに答えられなかったわたしに「ちゃんと計算しておかなくちゃダメだよ!」と、怒った口調で、ふざけてわらった。はじめてタイパンツ展をやらせてもらったときも、北出さんは初日の賑わいをバックヤードからずっと見ていた。お客様の入りと反応を終日みてくれていた北出さんは、閉店後に「これはうまくいけば化けるかもしれないぞ〜?」と茶目っ気たっぷりに言った。「名前はタイパンツにとらわれなくても、いろいろ調べたら日本にはモンペ、袴、カルサンなど、いろいろあるみたいだよ。みもちゃんも調べてみなさい」、とも。
ものを売ることを考えるとき、いつもこのふたりをおもう。彼らのメガネの奥でひかるつぶらな瞳の力強さが、時にいまでもこわいほどに。ものを作って売ることをはじめると、大抵は「なんとなく売れればいいかな」とか「値付けはずかしい〜」なんてことをよく聞く。自分もそんなことをよくおもっていた。一生懸命なんてダサい、みたいなバカみたいなプライドもかなりあった。1秒でもはやく捨てるべきだった。買ってくれる人や場所を提供してくれた人、家族、総じて応援してくれている人たちに、とても傲慢で嫌なやつだった。一番は自信の無さと、いつでも逃げられるようにという甘えがあったのだろう。失敗しなくないし、本気になるのがこわかったのもある。ふりかえると逃げ道や回り道ばかりして、寄り道のながい人生だ。失敗は反省して、学びを忘れず、成長しつづけたい。実直に、真剣にものを作って、誠実に売っていきたい。ものをつくって売るということ、それはわたしにとって、時間と魂を削るということ。