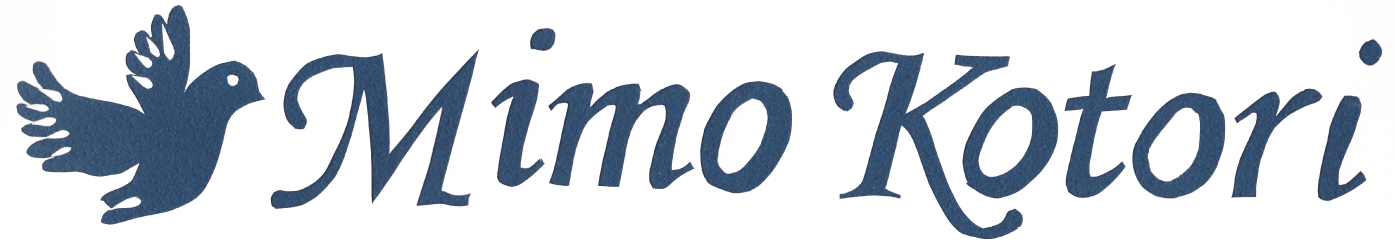日曜日の夕方、DAILYの馬詰さんとディモンシュでコーヒー。今ではDAILYの馬詰さんだけれど、出会った20年前はBORN FREE WORKSの馬詰さんだった。レンバイのnuinui 1stに、「はじめまして、ことりです」と会いにいったのは、わたしがまだ20代の頃。今はBORN FREE WORKSも、nuinui 1stもない。
月日の流れでしかつくることの出来ない、そして失うことのできないものは確かに存在する。豊かさと哀しみ、相反するけれどおなじ深さで。昨日は風に吹かれながら外のベンチで席が空くのを待っている間、とある文章の推敲(すいこう)のようなものを頼まれた。こんな日が来るのか、という感慨深い気持ちが入り混じる。当時のわたしはワークショップで文章をかくということに向き合っていた。今よりも、もっともっととんでもないレベルの散文や詩を書いていた。あれから長い時間をかけて本をつくり、気持ちを言葉にし、声に出して伝えることを繰り返してきてた気がする。頼まれて書くわけでも、依頼された仕事のために書くわけでもなく、じぶんのために、相手に伝えるために、言葉を綴ってきた。お金をもらうどころか、お金を払ってまで本をつくったりしてきた自分だけれど、「ものを書く人」とおもってもらえることは純粋にうれしい。
湘南にきたばかりの、20代だったわたしにとって、40代の人はだれもを遠くの先輩だとおもっていた。時を経て、その感覚には変化がおとづれた。先輩はおねえさんになり、おねえさんは、やがておねえちゃんみたいな存在になった今。憧れをもって東京から移住した湘南も、今ではもうずいぶん長く住んでいる。引っ越してきた当時に比べたら街はずいぶん変わったけれど、じぶんがこの土地へやってきたことで、風景を変えてしまった部分も少なからず、あるのだあろう。昨日は、そんなことをふとおもうような夕方だった。「半分食べてね」と言われたパフェを2本のスプーンでつつく。傾きそうで傾かないなプリンパフェにわらって、またコーヒーを口にする。思い出しわらいで、またわらう。わらって吹き出しそうになるコーヒー。わらいすぎて涙が流れたのに、ハンカチが見当たらない。スプーンを置いていた紙ナプキンを折りたたんで、しろいきれいな部分で涙をぬぐう。なんでもない日曜日の夕方に散りばめられた、いくつもの片鱗(へんりん)。