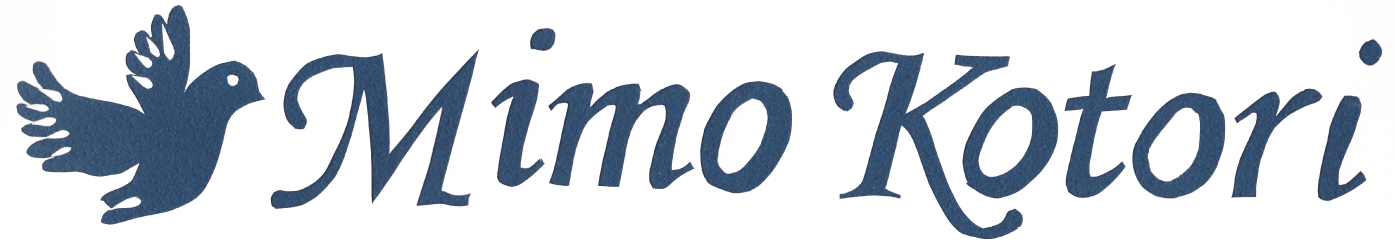クリスマスシーズンの銀座の夜はキラキラしている。4歳か5歳か、何歳ごろだったかは忘れだけれど、クリスマスシーズンに家族で銀座にいった夜のこと。買い物などをしたのだろうとおもうが、その終盤で父がとつぜん「俺は蟹が食べたい」と言い出して、行きつけと思しき店に行くと言い出した。母も一緒に連れていかれる様子だった。飲み屋だったので、父はこどもを連れて行きたくないと思ったのか、真相は定かではないが、「お前たちはここで待ってろ」と言われた。その飲み屋は銀座松屋の近くの、ビルの地下だった。私たちこども4人はビルの内側の、自動ドアが開いたり閉まったりする踊り場のようなところで待たされた。螺旋階段をさっさと降りていく父と、「え、え!?」みたいな母の後ろ姿を見て、「ママー!!!!(涙)」と思った遠い哀しい記憶。それ以来、しばらくクリスマスのキラキラした銀座恐怖症だった。その話を母にすると、たいてい口を押さえて爆笑している。「そんなことあった?ひどいいわね!ごめんなさいね、パパはわがままな人だから」と、たいていは父のわがままが原因になっている。「そっか、そうなんだ。パパはわがままだもんね」と長い間納得していたが、最近になって、ママもそう遠からずだったのでは?と思う時がある。父はいつでも、こどもたちのことは「ほっとけよ」と言っていたと、母から聞いた。おかげで伸び伸び育ったが、エピソードを聞くと、結構ひどいことがちらりほらり。
「みもちゃんは昔から声がきれいで、『ママ!』って呼んだ声を聞いた人から、『ことりちゃん、この子はジャズシンガーにしなさい!』って言われたのよ」と聞いた。なんて素敵なエピソードなのかと、それは誰なのと聞くと、銀座のゲイバーのママだという。聞けばその日は、家にいた父がとつぜんに行きつけのゲイバーに行こうと言い出したそう。まだ、さすがに小さな末っ子のわたしは置いていけない。苦肉の策だったのか、結果的にわたしは父と母と一緒に、ゲイバーに連れていかれたそうだ。わたくしは果たして何歳で銀座のゲイバーに足を踏み入れたのでしょうか。そもそも、あんよはヨチヨチできたのか。母はいつも、この日の出来事をたのしそうに話す。だから、聞いているこっちまでつい笑ってしまう。普通に考えて、ぜんぜん笑いごとではないけれど。
鹿児島の海辺の田舎で育った母にとって、真面目でやさしいお父さんの娘として育った母にとって、父はどんなに変わり者に映ったことだろう。子どもは親を、その家庭環境を基準に「これが普通なんだ」と思って育つ。大きくなるに連れて、あれ?あれ?と他の家庭との違いに気がつきはじめて、思春期になると「普通がよかった」、「普通ってなに」と人生を模索していく。いつか家族のことを本にしたいとおもう時がある。誰の参考にもならないが、娘には残したい気持ち。だっていずれ、忘れてしまう。みんな消えてしまうから。
最近おもうのは、誰のために日々文章を書いているかということ。ずっと、自分のためと思っていたけれど、最近は、娘に書き残している部分もあるのかなと思うときがある。それは娘が面白がって過去のわたしの文章を読んでいる姿も少なからずある。加えて、娘は娘で、文章をたのしそうにパソコンで書いている姿をたびたび見るから。わたしの母も、言葉を、手紙を、綴るのがだいすきな人だった。父もそうだった。実家の片付けをしていたとき、母に宛てた、万年筆で書いた膨大なラブレターが出てきたとき、「へー」とおもったのも記憶にあたらしい。自費出版でまで本をつくったり、こうして文章を書いていると「たくさん本を読んできたの?」とよく聞かれる。答えはノー。その代わりに、たくさん会話をしてきた。六人家族だったので、誰かと誰かが喧嘩したり、それを仲裁したり。朝から晩まで騒がしい家だった。父の態度が納得いかないと、抗議文を書いて、父の寝室のドアに貼り付けたりもした。
誰かの言葉ではなく、わたしはわたしの言葉をもつ。だからこうして、書きたいときに、書いているのだ。記憶を残すため、気持ちを主張するため、ありがとうを伝えるため、たとえばあの日のさようならのために。わたしがわたしを慰めるために言葉はあって、いつでも、わたしに寄り添っている。