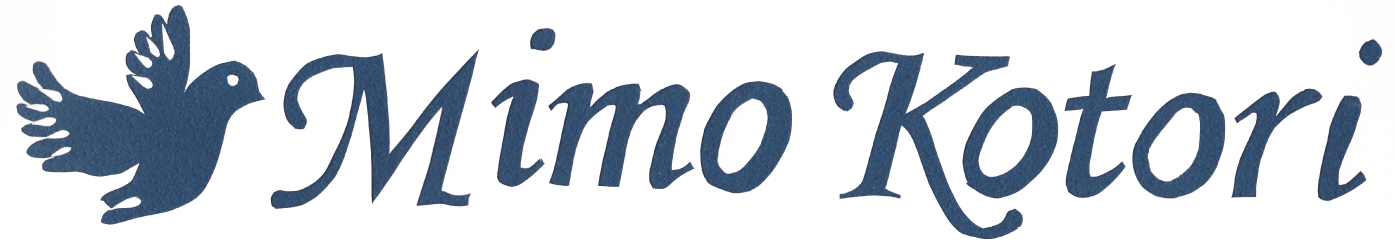「なんで寝顔ばっかりとるんだろう」
父はむかし、フィルムカメラで膨大な写真を撮っていた。ゴルフコースでのショット写真、好きな車のカーショーでは同じような角度で同じような車の写真、日常で食事を囲んでいるときの、どうでもいいような家族の写真などなど。フィルムは、近所のセブンイレブンで現像をたのんでいた。数日すると、写真が出来上がる。それを、父はこどもだちに引き取りにいけと、お使いをさせた。
父は、わたしたち子供の寝顔をやたらとたくさん撮っていた。幼い頃は、「こんなのじゃなくて、起きてるときをとってよ!」と腹立たしくおもっていた。しかし、娘が生まれて父の気持ちがわかった。こどもの寝顔ほどかわいいものはない。起きないように、そっとスマホで写真を撮るたびに、父のことを想う。
わたしはむかしからママっ子だった。美人で思いやりがあり、分け隔てなく人に優しいママ。目があうと外人みたいに口角をあげて笑う仕草も、かわいい声も、おしゃれなところも、香水の香りもマニキュアも、その全部が好きだった。いまも大好き。いっぽうの父は、昭和の破天荒を絵にかいたような人で、家族はいつもふりまわされていた。こどもが4人いて、6人家族なのに2ドアの車に乗るような人で、オレ様が一番大好き。実家には父のレコード部屋があり、壁一面のレコードと今考えると異常なデカさのスピーカーがあった。その部屋にはいり、すこしでも走ろうものなら「針がとぶだろ!」と叱られたし、気分が滅入るほどの爆音でジャズが流れるこわい部屋。
大学生になって車の免許をとったとき、友人たちからは「家の車でお父さんと練習してる」みたいなことを耳にしていたが、父は「パパの車にはぜったいに乗せない」といい、愛車を守っていた。そういう人だったから、「こういう人とだけは結婚しない!」と常々思っていた。自分勝手で頭にくるのに、とつぜん変なことを言って笑わせたり、おもしろいことをいう間合いが絶妙だったり、猫のポーズで「にゃー」と近づいてきたり、悔しいけれど、人たらしという言葉がぴったりで。本当に気まぐれな猫のようで、甘えたり、怒ったり、気分次第で、とつぜん家族にプレゼントを買ってきてくれたりもした。いらないものもあったけれど。
娘が生まれてから、「ママはさあ」「ママってさあ」と身の振り方を注意されるたびに、薄々気づいてしまった。わたしは父にとても似ているらしい、ということだ。パパのせいで大嫌いだとおもっていたのに、大人になるにつれてジャズやレコードが好きになってしまったし、父が好んでいたエルメスにも興味を持ってしまったし、「なんだかんだいって結局は銀座だぞ」も、言わんとすることがわかってきた。父が言っていた言葉で忘れられない言葉が二つある。一つは、「魚も人も、目が死んでいる奴はだめ」。二つ目は、「仕事にはルンルンでいけ」だった。父は家業を継いでいて、親族もいたので苦労もおおかったはず。だけど、愚痴っているところを一度もみたことがなかった。「月曜日が待ち遠しい」ともよく言っていた。自宅に変な営業の電話がかかってくると、意外だけれどすごく優しくて、営業マンのはなしを一通り聞いたあと、「うちは間に合ってるんだ、ごめんね、ありがとね」と言って電話を切っていた。「そんなふうに子どもにも優しくしてくれよ」と心の中で思って聞いていたが、「アイツらも仕事だからね」と言っていた。「アイツはいいひとなんだよー」が口癖。学生時代のノリが抜けず、長い男子校生活をひきづったまま、仲間とはしゃいでいた。そういう、理解し難いアンバランスな感覚をもっていた。なぞなぞな人、なぞをときがたい父であった。そんな父もすっかり歳をとり、今ではエッジがとれて、穏やかな顔をしている。よくみたら、優しい顔をしている。
母はどうして父を選んだのか、それこそが永遠の謎だ。ワイドショーなどで内田裕也さんが出てくると、母はいつも「パパににてる」と、ロックンローラーをとっても肯定的に眺めていた。もしも娘が生まれなかったら、父が撮るわたしたちの寝顔の写真は、永久的に未解決の謎だった。だんだんとわかってきたことは、父はめちゃくちゃだったけれど、とてつもないロマンティストで、その姿をしっているのは、母だけなのかもしれない。結婚すると勝手に決めて、ひとりで話をすすめてしまった父。時代が時代ならストーカーと言われてもおかしくなかったかもしれぬ父。母もさぞや困ったことだろう。そういう手口も、わたしと似ている。遺伝とは、困ったものです。にも、12歳のおたんじょうびおめでとう。ありがとう、ママが知るよしもなかったことをおしえてくれて。