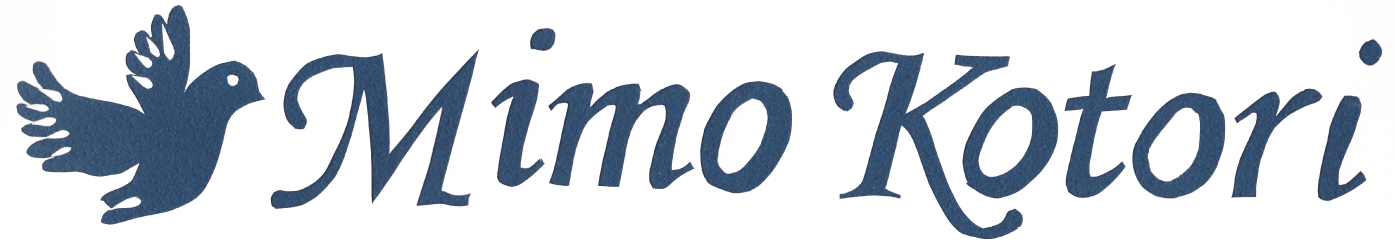東京へ。鹿児島から従姉妹がきており、姉といとこ、わたしの三人で母に会いにいく。従兄弟は学生時代に東京で暮らしていたこともあり、当時から母を慕ってくれていて、母も従姉妹を可愛がっていた。昨日は4人でのんびりとおしゃべり。またくるねと玄関でバイバイをするとき、施設の方に声をかけられ「おかあさまは昔から穏やかだったんですか?」と聞かれた。「そうなんです、母から褒められますか?」とふざけて聞くと「労(ねぎら)いの言葉しかかけられません。いつも、なにをしても『ありがとう』って言ってくれます」と言われた。ああ、こんな会話はわたしにとって生涯の宝物だなと、心の中にあるノートにペンを走らせる。母はそんな会話も、わたしが渡された言葉もしらない。こんな人生をおくれたらいいなと、心底おもった。おおきな評価ではなく、誰かの笑顔をつくる人生。誰にも知られないようなちいさな称賛。それすらもじぶんの手ににぎりしめず、どんどん配っていくような人生。「親切にしてもらったら、お返ししなさい。同じ相手じゃなくてもいいのよ、めぐっていくから」と母はよく言っていたが、その言葉をふと思い出した。その後三人でお茶をしていたのだが、長女に対しては、母はもっと厳しかったよね、という話になった。確かに兄と長女に対しては「きちんと育てなくては」、という意識があったのかも知れない。わたしは四番目の末っ子なので、そのような意識も薄れていたのだろうか。あるいは母自身に変化があったのか、もはや知る由もないが、違う視点で育ててもらった感じがある。正解ばかりの子育てではなかっただろうと思うし、若くして結婚した母には母の苦労もあったはず。両親から譲り受けたものはたくさんあるので、忘れないうちに言葉に残していきたい。自分自身に無意識にインストールされたものを、娘がまた、彼女の感性で受け取っていく。そうして手渡されていくことで、わたしたちの短く、しかし尊い命が続いていく意味は、秋のように深まっていくのだろう。紅葉する木々の葉は、やがてはらはらと落ちていく。それでいい。わたしたちは言葉をつかってもいいし、使わなくてもいい。肉体が存在しても、しなくてもいい。過ぎ去っていった言葉、笑顔、風景、そういうものを思い出せる心こそが永遠の光であり、それをきっと、人は豊かさとよぶのだろう。